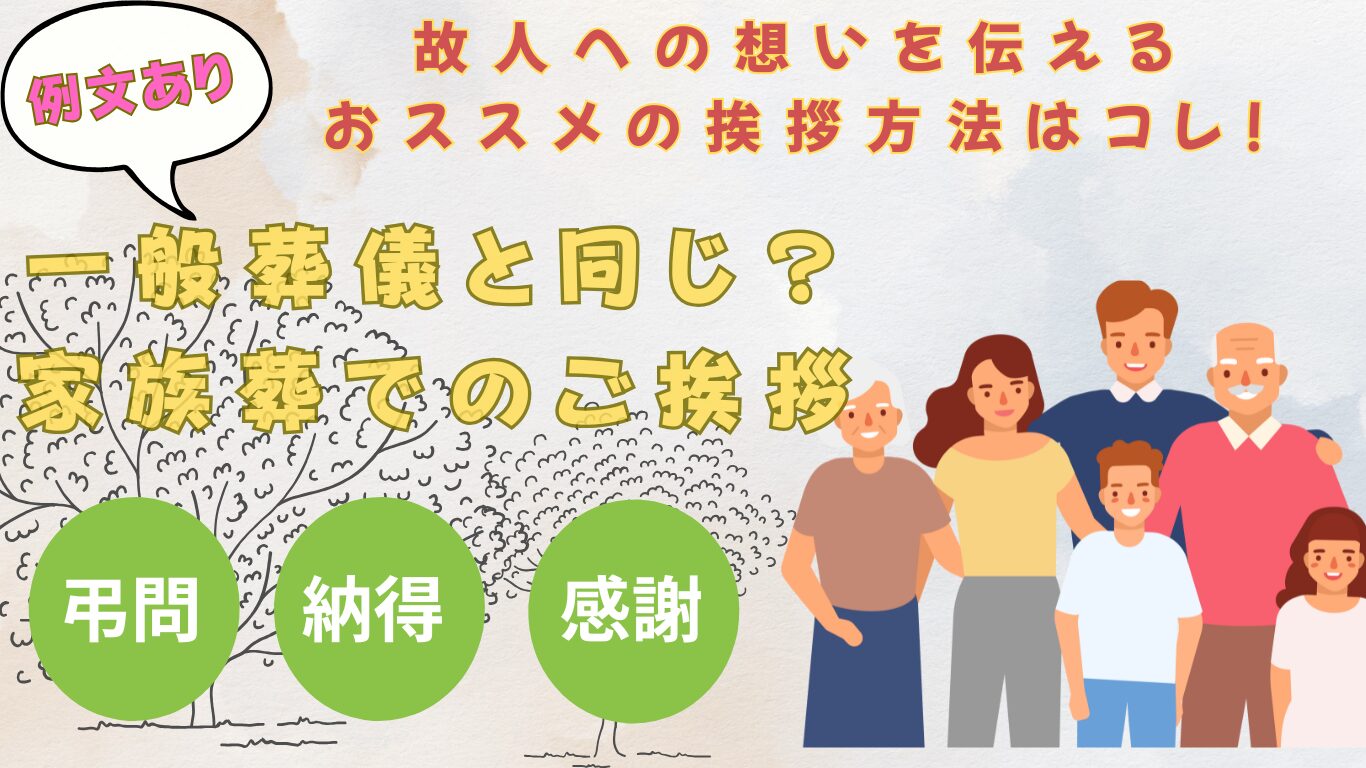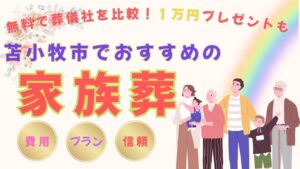家族葬の喪主挨拶は悲しみのなかでも粛々と行わなければなりません。
とくに家族葬の場合、一般葬とは異なる、特別な温かみと心遣いが求められる事が多いです。
なぜなら弔問される人はより身内に近い方が多く、形式的な挨拶ではなく、故人への感謝と愛情を込めたメッセージを伝える場として考えているからです。
そこで今回は家族葬の喪主挨拶についての悩みを解消し、心温まる挨拶を作成するためのあいさつ文について、例題も交えてご紹介していきたいと思います。
家族葬の喪主挨拶、一般葬とはここが違う!

多くの方が、葬儀の準備に追われる中で、「喪主挨拶」について頭を悩ませるのではないでしょうか。
とくに近年増えている家族葬の場合、「どんな挨拶をすれば良いのだろう?」と戸惑われる方も少なくありません。
「喪主挨拶」と聞くと、どうしても格式ばった、形式的なものを想像しがちです。
しかし、家族葬における喪主挨拶は大きく異なると認識しておくことが大切です。
なぜなら、一般葬と家族葬では、ご参列いただく方の顔ぶれが大きく違うからです。
一般葬では故人の生前の仕事関係の方や、遠縁の方など、普段あまり接点のない方も多くいらっしゃいます。
そのため、喪主挨拶も、ご来場いただいたことへの感謝や、今後のご支援のお願いといった、より社会的な側面が強く求められる傾向にあります。
一方、家族葬は、文字通りご家族やごく親しいご親族、友人のみが参列するプライベートなセレモニーがほとんど。
そこに集まる方々は、故人と長く付合いがあり、ともに悲しみを分かち合える間柄の方が多いはずです。
だからこそ、家族葬の喪主挨拶は、形式的な言葉よりも、故人への感謝の気持ちや、思い出を語りかける、温かい雰囲気のものが求められます。
家族葬での挨拶(一例)



それでは、家族葬において、どのような挨拶がよいのでしょうか。
「お忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございます」
といった定型句ももちろん大切ですが、それ以上に、故人とのエピソードや、ご自身の素直な気持ちを言葉にすることで、参列者の方々にも故人への想いがより深く伝わるはずです。
そこで、ここでは家族葬での挨拶におすすめしたい流れをご紹介します。ご自身の状況や故人との関係性に合わせて、アレンジしてご活用ください。
心が伝わる!家族葬の喪主挨拶
サンプル1:故人への感謝と、参列者へのねぎらいを込めて
「皆様、本日は亡き父〇〇の家族葬にご参列いただき、誠にありがとうございます。
父は、私たち家族にとって、いつも明るく、そして何よりも頼りになる存在でした。特に、私が困っている時には、いつも優しく寄り添い、温かい言葉をかけてくれました。その存在がどれほど大きかったか、今、改めて実感しております。
生前は、皆様にも大変お世話になりました。父がここまで生きてこられたのも、ひとえに皆様の温かいお支えがあったからこそと、心より感謝申し上げます。
父は、最期まで家族に心配をかけまいと、私たちに笑顔を見せてくれました。その姿は、私たち家族にとって、これからもずっと心に残るでしょう。
本日は、お忙しい中お集まりいただき、本当にありがとうございました。どうか、ゆっくりと父との思い出を語り合っていただければ幸いです。」
サンプル2:故人の人柄を伝え、感謝と別れの言葉を
「皆様、本日はお忙しい中、母〇〇の家族葬にお集まりいただき、ありがとうございます。
母は、本当に明るく、そしていつも周りの人を気遣う優しい人でした。料理が得意で、私たち家族だけでなく、親戚やご近所の方にも、いつも手料理を振る舞って喜ばせていました。
母の作った〇〇(具体的な料理名)は、もう二度と食べられないと思うと、寂しさが募ります。
生前は、皆様にも大変温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。母も、皆様との出会いを何よりも大切にしておりました。
これから、母がいない生活は、想像もつきませんが、母が残してくれたたくさんの思い出と教えを胸に、私たちは前を向いて歩んでいきたいと思います。本日は、ありがとうございました。どうぞ、皆様、母を偲びながら、心ゆくまでお過ごしください。」
サンプル3:思い出に触れ、別れの悲しみと未来への思いを込めて
「皆様、本日は、亡くなりました〇〇(故人のお名前)の家族葬にご参列いただき、ありがとうございます。
〇〇は、私にとって、かけがえのない存在でした。いつも私のことを一番に考え、時には厳しく、時には優しく、私を支え導いてくれました。特に、〇〇(具体的な思い出やエピソード)の時には、本当に〇〇に助けられました。その時のことは、今でも鮮明に覚えています。
突然のことで、まだ信じられない気持ちでおりますが、皆様にお集まりいただき、〇〇を偲んでいただけることを、〇〇も喜んでいることと思います。
生前、〇〇が皆様からいただいたご厚情に、心より感謝申し上げます。
〇〇との思い出を胸に、私たちはこれからも生きていきます。そして、いつか私たちも〇〇のように、周りの人を大切にできる人間になりたいと思います。
本日は、本当にありがとうございました。どうぞ、ごゆっくりと、〇〇との最期の時間をお過ごしください。」
サンプル4:故人が望んでいたことや、生前の言葉を引用して
「本日は、亡くなりました〇〇(故人のお名前)の家族葬にお集まりいただき、誠にありがとうございます。
〇〇は生前、いつも『〇〇(故人の口癖やポリシーなど)』と申しておりました。その言葉の通り、〇〇は私たちにたくさんのことを教えてくれ、その生き様を通して、多くのことを示してくれました。
病気が発覚してからも、〇〇は決して弱音を吐かず、私たち家族に笑顔を見せてくれました。最期まで私たちを気遣ってくれた〇〇の優しさに、感謝しかありません。
皆様には、生前、〇〇が大変お世話になりました。〇〇も、皆様との出会いを心から喜び、大切にしておりました。
〇〇が安らかに眠れるよう、どうぞ、皆様、心の中でお別れをしていただければ幸いです。本日は、お忙しい中ありがとうございました。」
「一般葬儀と同じような挨拶にしたい」と考える場合
これからセレモニーを控える喪主さまには「家族葬でも、一般葬と同じような形式的な挨拶で問題ないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
たしかにごく限られた身内だけであっても、きちんと締まった挨拶をしたいというお気持ちもよくわかります。
しかし、ご参列いただく方々の顔ぶれによっては、「少し儀礼的すぎるのでは?」と感じられることもあるでしょう。
例えば、故人のご兄弟や特に親しいご友人だけであれば、より砕けた口調で、思い出を共有するような挨拶の方が、心に響くかもしれません。
一方で、遠縁の親戚なども含まれる場合は、ある程度の丁寧さも必要になるでしょう。
このように、家族葬に誰が訪れるかによって、挨拶のニュアンスを若干変えて調整することが必要です。
ですが大切なのは、参列してくださる方々が、故人を偲び、心温まる時間を過ごせるような配慮です。
喪主としての挨拶は、たしかに責任が重大です。ですが家族葬では故人への感謝と愛情を伝えることを最優先に考え、その上で、参列者との関係性を考慮しながら、言葉遣いや内容を調整してみてください。
家族葬だからこそ、心温まる挨拶ができる
家族葬は一般葬に比べて、より身内が集まり親しい集まりの中で行われることがほとんどです。
だからこそ、故人への挨拶も形式的なものにとどまらず、心のこもった温かいものになるのは必然と言えるでしょう。
飾らない言葉で、故人への感謝や思い出を語りかけることは、故人への最高の供養となります。
そして、それはきっと、悲しみに暮れるご遺族の心にも、温かい光を灯してくれるはずです。
上記にサンプルをご紹介しましたが、あなたの故人への想いを存分に表現できるようなアレンジをしてみましょう。それが、あなたと故人との絆、そして思い出を、参列者の皆様とともに分かち合う、かけがえのない家族葬となることでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。当サイトでは家族葬の喪主挨拶をより個人的で心温まるメッセージがよいとおすすめしました。
形式的な言葉遣いよりも、故人への感謝の気持ちや、思い出のエピソードを交えることで、参列者の心に響く挨拶となります。
このように家族葬が注目を集めている点は数多くありますが、選ばれる方の多くが低予算で一般葬儀に近いセレモニーが行える点に魅力を感じています。
では、どこで葬儀社を選べばいいのでしょうか?
当サイトでは評判の良い家族葬を無料で選べる「安心葬儀」をおすすめしています。
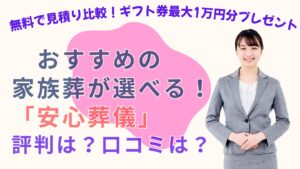
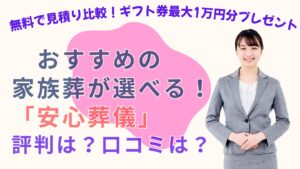
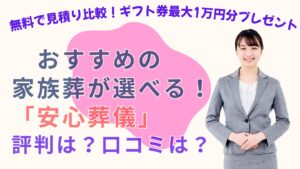
今回ご紹介した例文を参考に、ご自身の言葉で、故人への愛情を伝えてみてください。それが、故人にとって最高のお見送りとなり、遺族にとっても、心安らかなお別れの時間となることを願っています。