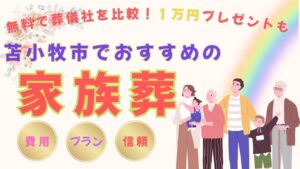最近、家族葬という形の葬儀が増えてきました。
一般葬儀のルールは分かるものの、家族葬に招かれた場合「香典はどうしたらいいのか」迷う方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、家族葬の香典に関する基礎知識から、お金の額の決め方、渡し方のポイント、気をつけるべきこと、そして香典の代わりにできる選択肢まで、幅広く解説します。
家族葬における香典の正しいマナーを理解し、適切に対応できるように準備しましょう。
家族葬における「香典の基本ルール」とは?

まず家族葬についてですが、これは故人の近親者だけで行う小規模な葬儀のことを指します。
一般的な葬儀と比べて、参加者が限られ、よりプライベートな雰囲気で行われるのが特徴です。
家族葬の主な特徴は少人数制(親しい友人や親族)であること。さらに故人や遺族の意向を尊重し、心のこもったお別れができる点です。
- 参加者が限られているため、故人との思い出を共有しやすい
- 葬儀の費用が抑えられる
- 故人の生前の希望を反映しやすい
以下の表は葬儀の種類ごとの割合推移です。ご覧のように一般葬儀よりも一日葬や家族葬を選ばれる方が増えています。
| 年 | 一般葬 | 家族葬 | 一日葬 | 直葬・火葬式 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 58.9% | 31.3% | 3.9% | 5.9% |
| 2017年 | 52.8% | 37.9% | 4.4% | 4.9% |
| 2020年 | 48.9% | 40.9% | 5.2% | 4.9% |
| 2022年 | 25.9%* | 55.7%* | 6.9% | 11.4% |
| 2024年 | 30.1% | 50.0% | 10.2% | 9.6% |
-
2015〜2020年:徐々に「家族葬」が増加し、「一般葬」は減少傾向でした(家族葬:31.3 % → 40.9 %)。
-
2022年:コロナ禍の影響で家族葬が劇的に増加(55.7 %)、一般葬は急落(25.9 %)しました。
-
2024年:感染対策の緩和により一般葬が若干回復(30.1 %)したものの、家族葬が引き続き過半(50.0 %)を維持しています。
※鎌倉新書「第2回~6回お葬式に関する全国調査」による
以上のように、この数年間で「家族葬」は明確に主流となってきていることが読み取れます。
なぜ家族葬が増えているのか?



家族葬が人気となっている要因はいくつかありあり、主には以下のようなことが増加を後押ししている理由です。
1.都市化・核家族化による地域関係の希薄化:地域との関わりが減り、親しい人だけで葬儀を行う傾向が強まったから
2.インターネットによる情報可視化と選択肢の拡大:価格や形式が明確になり、家族葬の選択がしやすくなったから
3.コロナ禍の影響:感染防止から小規模な形式の葬儀が主流となりつつあるから
4.参列者数の減少:2013年の約78人から2024年には38人程度に減少し、必要以上の規模を避ける流れに。
5.費用面での合理性:家族葬(約105.7万円)が一般葬(約161.3万円)より安価である。
6.価値観の変化:「親しい人と心を込めて送る」という葬儀のあり方が支持されてきた
とくに人口減少や、コロナの影響からいままでのライフスタイルが変化していることがわかっており、結果、以前よりも少人数制で行える家族葬が注目されることになっています。
香典は「故人への弔意」を表すもの



それでは、香典について説明しましょう。
香典は、故人に対する弔意を表すための金銭的な贈り物です。香典を通じて、故人の冥福を祈るとともに、遺族への支援の意を示すことができます。
- 故人への感謝の気持ちを表す
- 遺族への経済的支援を行う
- 参列者同士の絆を深める
この香典の他にも、供物、供花などがありますが、いずれも故人への弔意を表す手段です。ですが、それぞれの役割やマナーは異なります。
- 香典:金銭的な贈り物で、遺族への支援を含むもの
- 供物:食べ物や飲み物を供えることで、故人を偲ぶもの
- 供花:花を供えることで、故人の冥福を祈るもの
これらのマナーを理解し、適切に対応することが大切です。家族葬に参列する場合には、故人にどのような弔意を送るか、考える目安としてみてください。
家族葬における香典の相場と金額の平均は?



それではここで、香典の相場をみていきましょう。
一般的に、家族葬では参列者が少ないため、香典の金額も低めになります。一方で、一般葬儀では規模が大きく、参列者が多いため、香典の金額が高くなる傾向にあります。
| 葬儀の種類 | 香典の平均額(個人単位) | 平均参列者数 |
|---|---|---|
| 一般葬儀 | 1万〜3万円 | 50〜100人以上 |
| 家族葬 | 5000円〜1万円 | 10〜20人 |
上記はあくまでも参考例であり、香典の金額は状況に応じて柔軟に設定することが求められます。
補足:香典を辞退する場合の考慮点とマナー
家族葬では遺族の意向から「香典を辞退」されるケースもあります。この場合は遺族の意向を尊重し、以下の点に注意が必要です。
- 香典を辞退された場合は、無理に渡さない
- 代わりに供物や供花を考える
このように故人への弔意を表す方法は他にもありますので、柔軟に対応することが大切です。
香典の用意と渡し方のマナーについて



家族葬や一般葬における香典には、いくつかのマナーがあります。
香典袋の選び方や、渡すタイミングなど、注意すべきポイントを押さえておくことで、失礼のない対応が可能です。
特に、香典袋の選び方や表書きの基本を理解しておくことが重要です。
とくに以下のポイントを押さえておきましょう。主には以下のようなことがあります。
・香典袋は丁寧に扱うこと
・葬儀の際に直接渡すのが基本
・言葉遣いに注意すること
このように、香典を持参する際のマナーを理解しておくことで、失礼のない対応が可能になります。
香典を渡す際の言葉の例
- 「この度はご愁傷さまでございます。心ばかりですが、お供えください。」
「ご愁傷さまでございます」は、相手の悲しみを悼む丁寧な表現であり、「心ばかり」は、金額が少ないことへの謙遜の気持ちを表します。
- 「この度は、誠にご愁傷様でございます。どうぞ、お納めください。」
より簡潔で丁寧な表現です。
- 「この度は、本当に残念でした。〇〇様(故人のお名前)へ、どうぞ、お納めください。」
故人との関係が深かった場合など、気持ちを伝えることを優先する表現です。
さらに「ご冥福を心よりお祈り申し上げます」など、安らかに成仏される事を願う気持ちを伝えるとより丁寧です。
まとめ
いかがでしょうか。家族葬における香典に関するマナーや平均費用を知っておくことで、その後の関係性も豊かになります。
とくに一般的に家族葬の香典平均を大きく上回ることは注意が必要です。多すぎてしまうと、親族を困らせる事もあります。
また、香典は現金を包むだけでなく、きちんと封筒に入れて、表書きには「御霊前」や「御仏前」と書きましょう。これも大切なポイントですよ!
家族葬は無理のない範囲で心を込めた香典を用意し、マナーを守りましょう。その一つ一つが、故人の思い出をより大切にすることにつながります。
気になるプランですが、家族葬を選ぶ際には「相場に見合ったプランはどのようなものか?」「口コミで評判のいいところはどこか」などが気になりますよね。
葬儀社はいろいろあります。ですので、ご親族に適した情報を一括で比較するため、当サイトは資料を無料で請求できる以下のサイトをおすすめしています。
■ お見積もり見舞金1万円
→葬儀にまつわる総合情報サイト【安心葬儀】
■ 資料請求で5万円の割引き
→家族葬するなら【家族葬のこれから】
上記2つがすべての家族葬でおすすめのサイトとなりますが、費用や特徴、口コミによる評判などから、ご親族に合った家族葬を見つけてみてください。